生成AIの出現により、AIの利用がとても身近な世の中になりました。
Chat GPTやGeminiなどで、日々の悩みや気になることを調べたり、文章や動画を作成したりしている人もどんどん増えています。
そんな中、生成AIの上をいく「自律型AI」というものが登場しました!
どういうAIなのか、生成AIとの違いやできること、注意点などを紹介していきたいと思います。
自律型AI(Agentic AI)とは

自律型AIとは、人間が設定した目標に対して自ら判断し行動できるAIのことです。
人間側の指示がなくても、目標達成のために必要な行動を自分で選択し実行できます。
情報収集・意思決定・行動実行・学習と改善行動を自分で行うため、人間は目標設定をするだけでいいのです。
自律型AIを活用することで、業務効率がアップし、人材不足も補うことができます。
仕組み
自律型AIの仕組みは、組み込まれたLLM(大規模言語モデル。人間のように文章を理解し生成できるAI)を使って、目標達成に向けたタスクの生成、実行、結果の評価、計画の修正を繰り返しながらタスクを実行します。
以下が、自律型AIのワークフローになります。
- ➀目標の認識:人間が設定した目標やタスクを受け取ります。
- ②タスクの生成:目標の情報を参考に、達成するためのタスクを生成します。
- ③優先順位付け:生成したタスクの優先順位を考えます。
- ④タスクの実行:計画に基づいてタスクを実行します。
- ⑤実行結果の評価:実行した結果を把握し、評価します。
- ⑥課題発見と修正:課題がないか確認し、必要に応じて新しいタスクを生成、実行します。
- ⑦内容の確認:必要に応じて、疑問点や修正の提案を人間に共有し、判断を仰ぎます。
生成AIとの違い
自律型AIと生成AIは、主に利用する目的に大きな違いがあります。
生成AIは文章や画像、動画などのコンテンツ生成を目的に利用されます。
生成AIは人間の指示を受けて行動を行うため、自ら考えて指示される前に動くということはありません。
一方、自律型AIは目標達成のための意思決定を行い業務改善することを目的に利用されます。
人間による指示がなくても、設定された目的に合わせたタスク生成や実行を自ら行います。
生成AIの成長も著しいですが、指示がなくても行動できるという点で、自律型AIの方が高い能力を持っています。
日本語で使えるの?
自律型AIは日本語で使うことはできますが、海外で作られたものが多いので、日本語よりも英語の方が正確に動作しやすいです。
Manusのように日本語に完全対応しているツールもあるので、日本語で指示を出したい場合は対応しているツールを選びましょう。
Manusについては、「おすすめの自律型AI 3選」の項目で紹介しているので合わせてご覧ください♪
自律型AIを導入するメリット4つ!

自律型AIを導入すると、どんなメリットがあるのでしょうか。
メリットを知って、自律型AIの魅力をもっと知っていきましょう。
業務効率化につながる
自律型AIは、目標達成のための行動を自ら行うだけでなく、その行動を休みなく瞬時に実行します。
人間は休憩や休みが必要ですが、AIには必要ないので24時間365日休みなくタスクを実行できます。
単純作業をAIに任せることで、従業員はクリエイティブな業務やより重要な業務に時間を割くことができます。
人材不足を補える
自律型AIは人間のように自分で考えて動けるので、一人の従業員として活躍できます。
単純作業をAIに任せることで、その他の複雑でクリエイティブな分野に人手を割くことができます。
個人事業主や小規模会社では、バックオフィス業務を自律型AIにやってもらうことで、メイン業務のみに集中できます。
自律型AIを導入することで人に依存することがなくなるので、退職や人手不足に対応できます。
人的ミスをなくせる
人間による作業では、入力ミスや判断ミスが発生しやすいですが、自律型AIではそのようなミスが発生することはありません。
業務を繰り返すごとに確実にやり方を学習するので、どんどん業務のスキルが上がっていきます。
これにより、ミスなく単純作業が完了できます。
状況に応じて行動できる
自律型AIでは、市場や商品需要の変化を敏感に把握できるため、人間が指示を出すことなく外部環境に応じてタスクを生成、実行してくれます。
突発的な事態にも臨機応変に対応できるので、顧客対応にも役立ちます。
このように、人手不足を補い休みなく即座にタスクを実行できるのが自律型AIのメリットです。
人手不足が深刻化しており、今後も少子化が進んでいくと言われている現代では、自律型AIのような存在が欠かせなくなってくるでしょう。
自律型AIの活用事例

自律型AIは、実際どんな業務で活用されているのか見ていきましょう。
これを知ることで、自社の業務で活用できるか確認できます。
バックオフィス業務
TODOリストの作成、報告書や請求書のひな型生成、経費の集計、スケジュール管理など、通常は時間のかかる事務作業を自動化できます。
入力ミスや手順ミスがないので、事務作業に時間が取られません。
マーケティング分野
トレンド分析、市場調査やコンテンツ制作、SNSの自動投稿、投稿内容の作成、競合サイトの分析など、マーケティング施策に必要な作業を行ってくれます。
作成前の情報収集から作成、投稿まで一貫して行ってくれるため、従業員はブランド戦略やディレクションなど、より高度な作業に時間を割くことができます。
IT・エンジニア分野
簡単なプログラミングの生成、バグの調査と原因解明、解決策の提案、API連携タスクの自動処理などができます。
障害が生じた時も、内容に合わせて瞬時に対応できるので、クレームを防ぐことができます。
簡単なプログラミング生成やトラブル対応はAIに任せて、より複雑な作業に集中できるようになるため、プログラマーの業務効率化が実現できます。
カスタマーサポート業務
既に導入され始めていますが、カスタマーサポートでのAI活用によりオペレーターの負担を軽減し、顧客満足度も上げることができます。
顧客からの問い合わせに対して瞬時に自然な回答をしてくれて、問題を解決します。
24時間365日稼働できるので、どの時間に問い合わせても対応できるため、顧客側も待ち時間なく回答を得られます。
加えて、過去の質問や対応を学習しているため、それを利用して顧客の状況にあった適切な回答を導き出せます。
これにより、オペレーターの省人化と労働時間の削減が実現できます。
自律型AI導入の注意点・課題

自律型AIはメリットが多いですが、課題や注意点も存在します。
導入前に確認して、課題のハードルが高すぎないか知っておきましょう。
導入コストが高額
自律型AIは生成AIよりも精度が高いツールのため、対応できる大規模な設備やシステムを用意する必要もあります。
その他にも、運用費用・保守費用・トレーディングデータの準備費用なども発生します。
初期費用だけでなく運用費もかかってくるため、導入ハードルが高いのが難点です。
専門知識が必要
自律型AIはほとんどの作業を自分で行いますが、最初の目標設定や途中の状況確認と修正は人間がやらなければいけません。
どのように設定すれば自律型AIが上手く稼働するかの知識が必要になります。
また、AIでは対処できないトラブルが発生した際、対応できる専門知識を持った人材が必要です。
専門知識のある人材がいない場合は、自律型AIを導入してもうまく使いこなせない可能性が高いです。
セキュリティ面での問題
自律型AIでは、個人情報や企業機密情報を取り扱う機会が多いです。
そういった重要な情報を保持したままインターネットやクラウドと接続することで、情報漏洩のリスクが高まります。
テキストだけでなく音声や動画などのさまざまな媒体でのデータを処理するため、不正アクセスされた場合かなりのダメージを受けてしまいます。
セキュリティ面を強化するため、セキュリティソフトの導入や通信の暗号化などを徹底しましょう。
法的・倫理的な側面の問題
自律型AIは人間の指示なく自動で判断してタスクを実行するため、万が一重大なミスが発生した場合、誰がどこまでその責任を負うのかという問題があります。
例えば、自動運転で事故が発生した場合、責任の所在はどこにあるのか、という部分でもめる可能性があります。
倫理的な側面では、学習内容によっては性差別や思想の偏りなどの不平等な行動が発生する場合があります。
誤情報の生成
AIは、誤った情報をあたかも正しいかのように生成してしまいます。
間違った情報でタスクが進行しないように、人間が確認して随時修正する必要があります。
AIは自信満々に情報を生成するので、気づかずにそのままタスクが進行しないよう、定期的な確認が必要になります。
おすすめの自律型AI 3選
では、実際に提供されている自律型AIツールを3つ紹介します!
導入を検討している場合は、まずこの3つのツールを知っていってください。
AutoGPT
AutoGPTは、オープンソースの自律型AIエージェントで、OpenAIの大規模言語モデル「GPT-4」が組み込まれています。
Significat Gravitasという個人のエンジニアがGithubで公開したところ、160k以上のスターを集め世界中で話題になったそうです。
以下がAutoGPTの特徴です。
- 自律したタスク実行
- メモリ管理機能
- 高度な言語処理能力
- API連携でさまざまなツールで使用できる
- インターネットアクセスと情報収集
- ファイルの読み取りと保存
- Pythonファイルの実行
- AutoGPTを活用することで、
- カスタマーサポートの自動化
- テキストの生成と管理
- データ分析とレポート作成
- 市場調査
などができます。
日本語対応:可。ただし、日本語にすることで性能が低下する可能性あり
料金:前払い制で、クレジットが0になったら使用できなくなります。
AgentGPT
AgentGPTは、Rewworkd AI社が開発し、OpenAIの大規模言語モデル「GPT-3.5」を基に構築された自立型AIエージェントです。
目標を設定することでタスクを生成・実行し、自問自答を繰り返しながら目標達成を目指します。
AgentGPTはブラウザ上で利用できるので、プログラミングが必要なく、専門知識がなくても利用できます。
以下がAgentGPTの特徴です。
- 高度な自然言語処理・理解能力
- 外部プラグインとの統合
- パフォーマンスのリアルタイム監視・分析
- メモリ管理
AgentGPTを活用することで、
- AIチャットボットの作成
- ワークフローの自動化(データ入力・ドキュメント生成など)
- カスタマーサポート
- Discordのボット(ユーザーとの対話や情報共有)
などができます。
日本語対応:日本語で入力はできるが、出力結果は英語
料金:フリートライアル=無料 プロプラン=月額40ドル エンタープライズプラン=カスタム
https://agentgpt.reworkd.ai/ja
ManusAI
ManusAIは、中国のスタートアップ「バタフライ・エフェクト」が開発した自立型AIエージェントです。
GAIAと呼ばれるベンチマークで高い評価を得ており、3段階のすべての難易度で最高水準を達成しました。
マルチモデルアーキテクチャを採用し、複数のトップ言語モデルの強みを組み合わせています。
招待性なので誰でも使えるわけではありませんが、注目度が高く人気の自律型AIエージェントです。
以下がManusAIの特徴です。
- 多モデル構成によるタスク分割と処理
- マルチエージェント構造による高度な問題解決力
- 高度な情報収集能力
- カスタマイズ性
- マルチモーダル対応(テキスト・画像・表・コードなど多数の形式に対応)
ManusAIを活用することで、
- 旅行ガイドの作成
- 市場分析
- 複雑な条件の不動産検索
- ウェブサイト制作
- 名刺デザイン作成
- ゲーム開発
- データ分析
- 品質管理と異常検知
などができます。
日本語対応:対応済み
料金:ベーシック=月額19ドル プラス=月額39ドル プロ=月額199ドル
このほかにも、たくさんの自律型AIエージェントが発表されています。月額は高いですが、支払えないほどの金額ではありません。
しかし、ランニングコストを考えたらなかなかの出費なので、よく検討してください。
完全自律型AIは実現できるのか
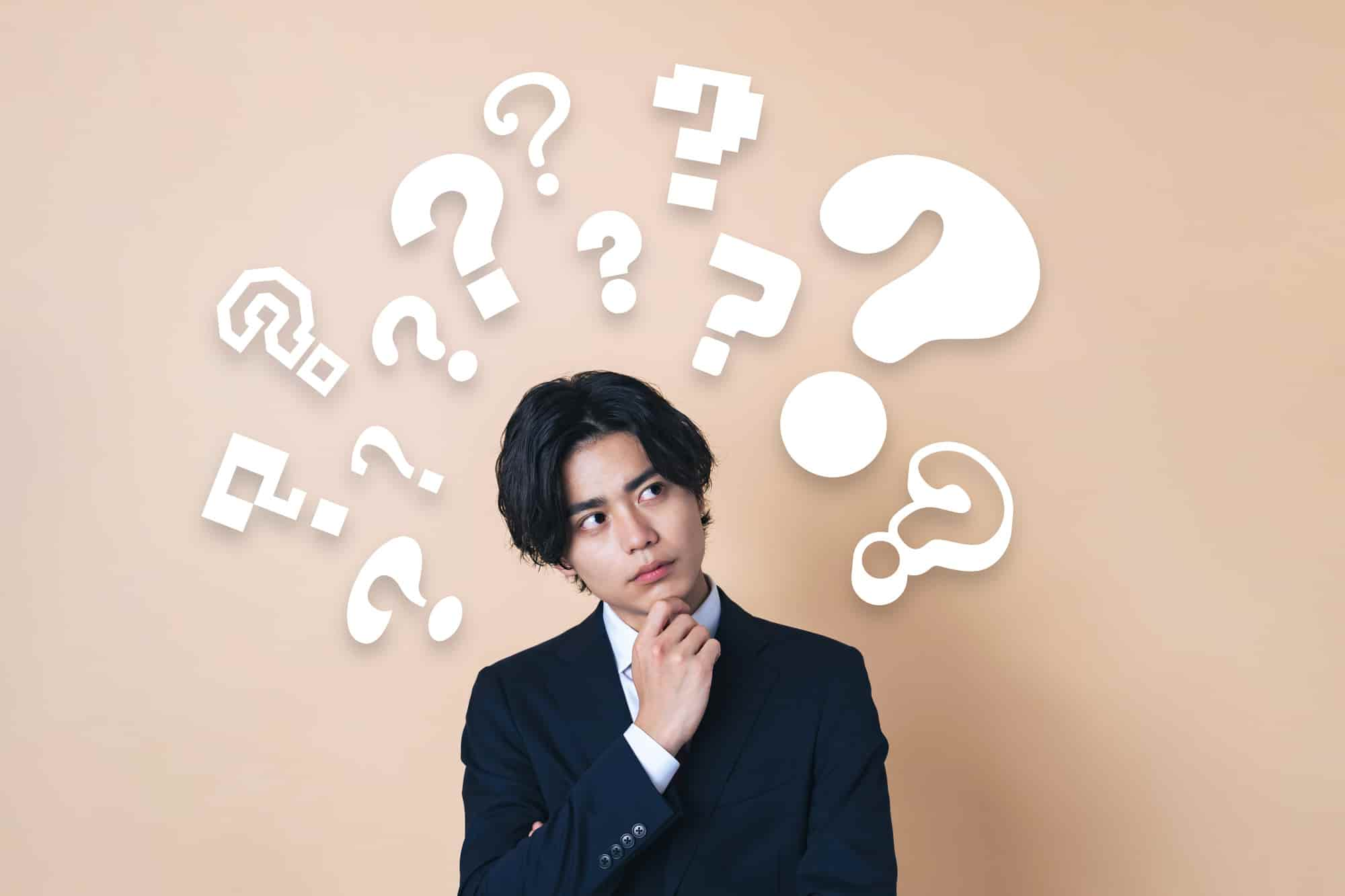
完全自律型AIとは、人間の介入がなくても目標を設定し、計画・実行・修正を行えるAIのことです。
すでに自律型AIが開発されていることから、完全自律型AIの開発も不可能ではないでしょう。
しかし、現実的にはまだ遠い未来の技術です。
自律型AIも、現時点で自我がなく、人間の感情や法律・倫理的な部分は理解していません。
必ず人間による指示・修正が必要になるので、今の段階から考えると完全自律型AIはまだまだ難しいと言えます。
まずは、生成AIと自律型AIを使いこなし、業務効率化や新しいアイデアの作成を実現していきましょう!


コメント